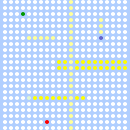

![]()
![]()
![]() あ行/江戸時代
あ行/江戸時代
![]()
江戸時代における庶民の左利きへの視点
川柳や雑俳に見られる左利きの姿
何かと世間では「昔は左ききは差別 された」とか「ギッチョなんて言われて嫌な視線をあびた」なんて話をしますよね? 確かに、私の幼少期にもそんな発言をよく耳にしましたし、もっと上の世代にもなると矯正は当たり前のようになされていたのです。確かに、左ききへの視線は冷ややかであることがままありました。
こうした左ききのおかれた状況について、最近では声高に左きき自身が叫ぶことができますが、さてさて、左ききへの蔑視って、近代以前の日本でも強烈なものであったのでしょうか?
今のようにメディアの発達していなかった江戸時代の日本をさかのぼってみると、ありがたいことに、川柳や都々逸、雑俳といった庶民の生活のシーンをユーモアとペーソスで彩
った短い「ことばあそび」を、先達は残してくれました。それらにふれてみると、やはり左ききへの蔑視はあったようにも思われますが、現代のように文明の利器が発達していなかったし、また教育という既製品としての人間を生産する場が庶民にはそれほど開かれていなかったぶん、もしかすると左ききへの視線は一時期の日本ほど厳しくなかったのでは・・・とも想像することもできます。
では、数こそ少ないですが、江戸時代の 川柳や雑俳から左ききの姿をピックアップしてみたいと思います。
◆「取直せ 美女よ不足の左箸」(「広原海」1703<元禄16>年より)
「あばたもえくぼ」といいますが、美女にとって「左きき」は、たんなる「あばた」にしか作者にはみえなかったのでしょうか? いずれにしても、いつの時代でも女性は世間的な「型」にはめられることを余儀なくされた感じが、この句でもみてとれます。
◆「忘れてはまた花嫁のひだり箸」(「千代見草」1692<元禄5>年より)
おそらく、嫁ぐまでは、家で左手で箸を持つことが許されていたのでしょう。けれど、外へ出れば、「ああこの子はしつけがなってない」と思われてしまったにちがいありません。
◆「いっそよい職人の子は左箸」(「三国力こぶ」1819<文政2>年より)
手先の器用さが求められる職人ですから、ああしつけがどうだとかこうだとかいう前に、「左ききは器用」っていうことで、ある程度はおおめに見てもらえたのでしょう。また、たいていの職人は男ですから、当時でもより左ききに寛容だったのかもしれません。いずれにしても、「ひだりギッチョ」という言葉の語源の一説に「左器用」が「ひだりギッチョ」といわれるようになったというのもありますから。名工・左甚五郎の伝説が、職人のあいだで浸透していたのではないかと思わせる句でもあります。
.......................................................................
(参考文献)
- 『見えざる左手』(大路直哉,三五館)
![]()
お得な/お役立ちな情報がいっぱいです

